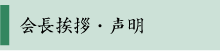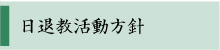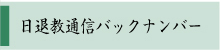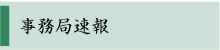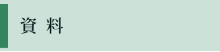25・26年度活動方針(2025年6月6日51回定期総会)
Ⅰ 特徴的な情勢と課題
1. 2025年は、日本の敗戦から80年目の年です。自公政権の下で、中国や朝鮮半島の軍備増強、情勢不安定化が煽られ、さらにアメリカからの圧力で安全保障政策が大きく変容させられ、防衛費の増大を招いています。同時に2025年は被爆から80年目を迎えます。2024年のノーベル平和賞は日本原水爆被害者団体協議会が受賞しました。広島・長崎に投下された原子爆弾により多くの命が奪われ、今日を迎えてもその被害に苦しめられている被害者が多くいます。日本政府は核兵器禁止条約の発効から4年を迎えた今日においても、未だに批准に向けて前向きな姿勢を示すことはありません。
ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルとパレスチナの深まる対立──世界の各地で、人々の命や暮らしが脅かされています。力による支配ではなく、対話と共存の道を選ぶことこそ、真の平和につながるはずです。そのことは、日本国憲法にも明記されています。私たちは、国や立場を越えてすべての人の人権が守られる社会を願い、その実現のために声をあげ、一人ひとりの尊厳が大切にされる世界を築いていかなければなりません。
アメリカ、トランプ大統領は、パリ協定からの離脱や環境規制の緩和など、気候変動への国際的な取り組みや多様性、ジェンダー平等に背を向ける姿勢を見せました。また、関税の引き上げや多国間協定の見直しを通じて、国際的な連携よりも国内の利益を優先する方向に傾きました。こうした動きは、世界的に、景気後退への懸念と金融市場の混乱が生じています。地球規模の課題に対する連帯の力を損なうものといえます。
2. 物価上昇が続いており、実質賃金(物価変動を考慮した賃金の購買力)は依然として厳しい状況にあります。厚生労働省が5月22日に発表した2024年度の実質賃金は前年度から0.5%減少し、3年連続のマイナスとなっています。
2025年の春闘では、平均賃上げ率が5.46%と、33年ぶりの高水準となりました。しかし、物価上昇の影響で実質賃金の回復には至っていません。特に、基本給にあたる所定内給与の実質値はマイナスが続いており、生活実感としての改善は限定的です。中小企業の賃上げに急ブレーキがかかりつつあることも指摘されています。政府は「構造的な賃上げ」の旗を掲げ、賃上げ企業への税制優遇措置などを進めていますが、暮らしは厳しい状態が続いています。
3. 2024年10月27日に投開票が行われた衆議院選挙の結果、自民・公明両党が少数与党となりました。今回の選挙は、自民党派閥の裏金問題を受けての選挙で、自公政権は不信任されたといっていい状況でした。自民、公明両党は公示前の279議席から64減らし215議席で、定数465の過半数(233)を割り込み、立憲民主党、国民民主党が議席を大幅に伸ばしました。減った自公、維新の票は、若年層を中心に国民民主党、れいわ新選組に流れたとみることができます。(資料1参照)
もう一つの特徴はSNSを使っての選挙活動です。とりわけ、動画配信による注目を集める手法による選挙活動です。
2025年度政府予算案は、戦後初めて参議院で修正された案が衆議院で再可決される形で成立しました。衆議院段階では、国民民主党の主張する「103万円の壁を178万円に」と日本維新の会が主張する「高校授業料の実質無償化」を「天秤にかけ」、修正額の少ない維新と合意し、成立通過させましたが、参院審議では衆院段階で一部修正した「高額療養費の上限引き上げ」について立憲民主党などのとりくみにより、参考人招致が行われ、「凍結」、立憲・維新を中心とする修正案が可決され、衆議院で再可決となりました。自民・公明の連立与党が衆議院で過半数を割り込むという政局のもと、与野党の協議と修正の積み重ねが、例年とは異なる予算成立の道筋を形作りました。
4. 「戦争をする国づくり」へ防衛費の拡大が続いています。2014年、自公政権は「集団的自衛権行使容認」を閣議決定しました。そして2015年9月、安保法案(戦争法案)を強行可決し、「専守防衛」に徹するとした国の防衛方針を切り替え、「戦争する国」へと変質させました。さらに「共謀罪」を強行(2017年6月)、「安保3文書(国家安全保障政策、国家防衛戦略、防衛力整備計画)」を改定(22年12月閣議決定)し、「先制攻撃」を可能とし、防衛費増額(GDP比2%)を明記しました。さらに「軍需産業支援法」(2023年6月)、「防衛装備移転三原則運用指針改定」(2023年12月)、と軍備増強路線を突っ走っています。2024年3月には英国、イタリアと共同開発する次期戦闘機の第三国への輸出を解禁する方針を閣議決定し、殺傷能力としては最強の戦闘機の輸出を可能としました。また日米で、「自衛隊による米軍基地等の共同使用、南西諸島を含む地域において、日米の施設の共同使用・共同演習・訓練を増加させる」「弾薬の南西諸島等島嶼部への分散配置を追求、促進する」として、急ピッチでミサイルを配備しています。
さらにトランプ政権による対日要求、特に安全保障分野への要求が強まり、一層の防衛費増が懸念されます。
5. 自民党議員・閣僚による人権侵害、資質を疑う言動が続いています。石破首相の「商品券問題」をはじめ、先日の江藤農水相の失言等、閣僚の資質が欠如した者が国政の中枢を担っている危機的状態が続いています。また、参院選において全国比例候補として公認するとした元総務政務官杉田水脈氏などによって繰り返される誹謗中傷、さまざまな差別発言・投稿、参議院議員西田昌司氏の「ひめゆりの塔」の展示内容を「歴史の書き換え」などと発言し、「沖縄の場合、かなりむちゃくちゃな(反日)教育をしている。自分たちが納得できる歴史を作らないと」と発言し、歴史の真実の改竄は行われているのは当然との発言がありました。このような状況を打開するためにも7月の参院選は、「政権選択」と位置づけ、とりくみをすすめることが重要です。
6. 2024年12月石破政権は、第7次エネルギー基本計画を発表し、その中で2023年では8.7%を占める原発について、2040年では20%程度を原発に依存すると発表しました。さらにこれまでの基本計画では、原発について「可能な限り依存度を低減する」としていた文言を「最大限活用」とかえました。
福島原発事故から14年、倒壊の危険性さえ指摘されている事故炉は、廃炉の道筋が見えてきません。福島原発事故によって発せられた「原子力緊急事態宣言」が解除されない中での、原発推進へ転換は許されません。
7. 今年は国連が3月8日の「国際女性デー」を提唱して50年。国際条約「女性差別撤廃条約」を日本政府が批准して40年。そして、日本で女性が参政権を得て80年となるジェンダー平等に関する大きな節目の年です。
女性差別撤廃条約は、1979年の第34回国連総会において採択され、1981年に発効しました。日本は1985年に批准しました。この条約の実効性を強化するために、1999年「個人通報制度」と「調査制度」を盛り込んだ「女性差別撤廃条約選択議定書」が採択されましたが、日本はまだ批准していません。2024 年9 月現在、条約締約国189 カ国中115カ国が選択議定書を批准しています。
8. 2025年1月24日に総務省が「令和6年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指標)を公表しました。それを受けて、厚生労働省は同日、2025年度の年金額改定について公表しました。2025年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(+2.3%)を基に、マクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)を適用した結果、1.9%の増額となりました。
年金額改定時に用いた物価変動率は2.7%でしたが、改定ルールにより、名目手取り賃金変動率が用いられました。
2024年7月に、5年に一度の年金健康診断である財政検証の結果が発表されました。検証の結果は、これまでの30年間の景気動向を引きずって行ったとしても、所得代替率50%を維持できることが明らかになりました。
今回の検証では、各世代の65歳時点における年金額の平均や分布の将来見通しが初めて示されました。特に、若年世代や女性の平均年金額の増加と低年金者の減少が示され、将来的な年金額の改善が期待されるとした検証結果となりました。
この検証結果を受けての2025年年金改正法案は、参議院選挙を前にして、野党、国民からの「負担増」批判を恐れ、取り扱いが定まっていませんでしたが、5月16日に政府案が提出され、審議が始まりました。
9. 日退教会員数の減少が続いています。2025年3月末、定年延長後初めての定年退職者が生まれました。定年退職後も再任用として働き続ける方が多くなっています。会計年度職員を含め、現役組合の組織対象とされている単会が多く、退教への加入に難しさを抱えています。現職組合との連携を強め、組織拡大に努めます。会員減少による会費収入減、物価高による経費増等から日退教財政状況は厳しく、組織財政確立委員会での検討をすすめます。
Ⅱ 具体的要求・当面の活動
1 憲法「改正」に反対し、平和・人権・環境が尊重される社会をつくります
具体的要求と活動
(1)憲法改悪を阻止し、立憲主義を取り戻すため、日教組・平和フォーラムとともに積極的に取り組みます。
各県・地域でとりくまれる「戦争をさせない1000人委員会」「総がかり行動」「さようなら原発1000万人アクション」の活動等に積極的に取り組みます。
「戦争法」「共謀罪」「特定秘密保護法」「土地利用規制法」の廃止を求めます。防衛費の大幅増に反対します。
(2)安保3文書に基づく「防衛産業強化法」、「防衛力強化資金法」による、兵器や軍事技術の輸出緩和政策に反対します。
(3) 普天間基地の即時運用停止、辺野古新基地建設阻止、ミサイル基地強化反対のために、沖縄県・高退教との連携をさらに強め、平和フォーラムに結集して取り組みます。
日退教沖縄交流団を派遣します。単会やブロック単位で沖縄の状況を理解し連帯を強めるための学習会や現地行動参加に取り組みます。また、全国各地の米軍基地反対闘争・合同演習反対運動に積極的に参加します。
(4) 日米地位協定の問題を追及し、改定を求めて取り組みます。
(5)「台湾有事」等軍事的緊張を煽る日本政府の姿勢を厳しく批判し、朝鮮戦争の終結、平和協定締結、朝鮮半島の非核化、東アジアの平和的安定を求め取り組みます。
(6) 朝鮮学校への差別的扱いに反対し、朝鮮学校への補助金・助成金等の支給停止反対運動をすすめます。朝鮮学校生徒の「高校授業料無償化」適用を求めて取り組みます。ヘイトスピーチを許さず、東アジアをはじめとする諸国の人々と友好と連帯・交流を深めます。
(7) 狭山事件の再審開始を求めるとともに、えん罪根絶に向けた司法改革・再審法改正、部落差別をはじめあらゆる差別解消に向け、人権侵害救済制度の確立を平和フォーラム等とともに取り組みます。
(8) 日教組「平和集会」「被爆二世教職員の会」活動に協力します。
(9)「女性差別撤廃条約選択議定書」の早期批准を求めます。女性の経済的自立と意思決定の場における発言力を高めることが、日本のジェンダー平等を実現するために不可欠です。「政治分野における男女共同参画推進法」の趣旨に沿った取り組みを地域ですすめます。さらに、「同一価値労働同一賃金」の実現を、女性の人権を国際的水準に引き上げる運動の要として取り組みます。
(10) 立憲主義を取り戻し、当たり前に生きることのできる社会をつくるため、各種選挙での日政連・各単会推薦候補の必勝をめざし取り組みます。
2025年7月に実施される第27回参議院選挙には、みずおか俊一さん(比例)、勝部けんじさん(北海道選挙区)、小島とも子さん(三重選挙区)を推薦し、勝利をめざします。各単会においても、みずおか俊一さん、勝部けんじさん、小島とも子さんの推薦を決定し、勝利するよう現退一致で取り組みます。
2 「教育改革」の危険性と民主教育を守るとりくみ
具体的要求と活動
(1) 憲法改悪反対の取り組みと連動し、復古的家族主義、国家主義的教育を許さないよう取り組みます。各地域で行われる県教組・高教組、関連団体の主催する学習会・集会に積極的に参加します。
(2) 国の定める「統一基準」による「検閲」検定に反対します。次期教科書採択にむけては、各地域における展示会への参加や学習会への参加に取り組みます。
(3) 学校の働き方改革のとりくみについて、日教組の提案する「7つの提言」実現に向けて、現退一致の取り組みを追及します。
(4) 貧困・格差を許さないため、教育の無償化への取り組みを強化します。
(5) 朝鮮学校へすべての制度的保障の適用を求めて取り組みます。
3 原発再稼働を許さず、脱原発に向けたとりくみ
具体的要求と活動
(1) 脱原発社会実現のため、政府のGX(グリーントランスフォーメーション)に名を借りた原発建て替え、再稼働・新設・稼働延長に反対します。各地での原発再稼働阻止等に向けて行われる諸行動に積極的に参加します。
(2) 震災を受けた地域の復興がさらに長期間かかることを念頭に、被災者の万全な生活・居住対策を政府・自治体に要求します。1947年制定のままの災害救助法の見直しを求めます。
(3) 原子力を「最大限活用」する第7次エネルギー基本計画に反対し、自然(再生可能)エネルギー普及のための法・制度の充実を求めていきます。
(4) 高速実験炉「常陽」の速やかな廃止、「もんじゅ」の廃炉作業の安全性確保、全ての原発を停止するよう求めます。
(5) 各地の自然エネルギー利用の取り組みに協力します。核廃棄物処分施設設置場所の政府による地方自治体への押し付けに反対し、廃炉費用、福島原発事故処理費用の原則事業者負担を求め、託送料に上乗せすることに反対します。「再生可能エネルギー」について、健康被害、自然への過度の負荷、自然破壊が懸念されるため、地元の意向に十分配慮することを求めます。
(6) 妊産婦、乳幼児・子どもなど若年者の被曝を防ぐ万全の対策を求めます。住民(避難民を含めて)の精密な医療検査と治療システムの確立を求めます。
(7) 「さようなら原発1000万人アクション実行委員会」の運動に参加し、各種集会等の成功をめざして取り組みます。
(8) 「連合・東北子ども応援わんぱくプロジェクト」「子どもの人権連・助成事業」の取り組みに協力します。高校生平和大使などの若者による運動の取り組みに積極的に協力します。
4 格差是正、社会保障の充実・発展、生活を守り、増税に反対するとりくみ
具体的要求と活動
(1) 抜本的な物価高騰対策を求めます。低賃金労働者、低年金者、子育て世帯、生活保護世帯、勤労学生などへのきめ細かな現金給付を中心とした支援の実施を求めます。
(2) 基礎年金はマクロ経済スライドの対象外とすることを求めます。短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、速やかにかつ抜本的に拡大すること、また国民年金保険料拠出期間延長(拠出期間を40年から45年に)を求めます。
(3) 介護保険の被保険者を医療保険加入者全体に拡大することの是非を検討します。ケアプランの有料化、「要介護1・2の総合事業移行」に反対します。 利用者負担原則1割維持を求めます。介護認定基準の見直し・改善を求めます。
(4) 公的皆保険制度を堅持させ、国民健康保険の財政基盤を確立し、低所得者に対する対策を講じて無保険者を発生させないことを求めます。医療を市場化する一部「混合診療」に反対します。「75歳以上の医療費定率負担2割の所得基準切り下げ」「所得に加え金融資産等を算定基礎とした患者負担」に反対します。「医療・介護両制度の違いを無視した横並びの負担増・給付抑制」をやめることを求めます。保険証を廃止して『マイナ保険証』に一本化強制に反対し、従来の保険証の使用継続を求めます。
(5) 子ども・子育て支援制度については財源問題を含め、真摯な議論を求めます。
(6) 高齢者虐待防止法の適正・的確な運用を求め、被介護者本人の意思を尊重する社会的介護をすすめる「介護共生社会」をめざして介護保険法改善要求を強めます。また、介護従事者の賃金改善を要求します。
医療・介護の切れ目のない地域包括ケアシステムを実体化するため、地域包括ケアの要である「地域包括支援センター」の機能と財政基盤の強化を求め地域密着型サービスを拡充することを求めて取り組みます。
(7) GPIF経営委員会の構成割合は労使代表を過半数とすることを求めます。
(8) 累進課税強化、金融所得課税是正を求め、消費税増税による、法人税減税肩代わりに反対します。金持ち優遇の軽減税率に反対します。「給付付き税額控除」の導入を求めます。
5 組織の拡大、強化のとりくみ
具体的要求と活動
(1) 親睦・交流・運動を通じて、退職者同士のつながりを強め、会員の孤立を防ぐよう努めます。現職組織との交流を重ね、組織拡大については現職の協力を得てすすめます。現職、再任用、退職者と切れ目のない組織化を追及します。
(2) 各単会は各現職組合に働きかけ退職者組織加入方針化を追求します。同時に共同行動を積み上げます。また、再任用者を退職者組織対象(現職組合との二重加盟も視野に)とするよう現職組合との協議をすすめます。
(3) すべての県に日退教組織を作り上げるよう日教組・各県単組と連帯して取り組みます。また、地方退職者連合組織未加盟単会は加盟を追求します。
(4) 毎年5月・6月を組織拡大月間として取り組みます。8月1日現在の組織現況・実態を調査します。組織拡大の取り組み、日退教・各単会の組織状況・実態については、10月の組織活動交流集会で交流します。
(5) 組織活動交流集会は、「組織」「平和」「教育・人権」「福祉・文化」を主題におこないます。すべてのブロックからのレポートの提出ができるように取り組みます。女性参加者の拡大に取り組みます。
(6) 五者合同学習会を日教組、全国退女教、教職員共済生協、日本教職員相互共済会共催で実施します。
(7) ジェンダー平等の観点にもとづき、女性会員の拡大、運動の充実に努めます。各種活動・集会、意思決定機関・役員への女性参画を高めるよう努めます。退職者連合のジェンダー平等委員会の活動に積極的に参加します。研究・検討・学習・論議を含めた運動を通じて日教組退職者組織の一本化をめざします。
(8) 各単会との緊密な交流・連携体制を強めます。各単会の運動に連帯し、支えあいます。「日退教通信」は会員の交流の場としての機能をさらに強化充実します。年に1~2回は、全会員に配布します。日退教ホームページの活用を充実し、運動の見える化を追求します。
(9) 学びたい人のためのマルクス・「資本論」学習テキストを推奨します。
(10) 日退教運動の拡がりと財政状況を踏まえ、組織・財政を見直します。引き続き、定期総会は隔年開催とし、定期総会を開催しない年は組織代表者会議を開催し、当面の活動を確認します。組織代表者会議の構成は各単会1(組織代表者)、ブロック女性代表者1(ブロック代表者)とします。
(11) 組織財政確立委員会(各ブロック代表者兼務)を引き続き設置し、将来の収入見直しに基づく、組織運営、事務局体制の検討を行います。
(12) 25年度日退教闘争カンパに取り組み、各種運動に活用します。
(13) 単会支援金による単会支援を行います。
(14) 退職後の会員互助を充実するため、教職員共済生協、日本教職員相互共済会、退職教職員生きがい支援協会などの運営・運動に参加します。
(13) 平和憲法を守り、脱原発社会の実現、社会保障制度の確立を求め、日教組、退職者連合・地公退、平和フォーラムに結集し運動に取り組みます。
日退教第51回定期総会 スローガン
教え子を再び戦場に送るな
□ 次期参議院・衆議院選挙に勝利し、改憲を阻止しよう。防衛費の増大に反対し、軍拡を許さずたたかおう。沖縄と連帯し、辺野古新基地建設をとめよう。日米地位協定の抜本的見直しをめざしとりくもう。
□ 東日本大震災・福島第一原発事故を風化させず、能登半島地震を記憶にとどめ、被災者・被害者の生活支援打ち切りに反対し、国・企業の責任を追及しよう。原発再稼働、新・増設、輸出に反対し、脱原発社会をめざそう。核兵器禁止条約の早期批准をめざしとりくもう。
□ 医療・介護・年金制度の改悪を許さず、社会保障制度の改善・充実を求めよう。格差社会の是正をめざしとりくもう。
□ あらゆるハラスメントを許さず、人権が尊重され、差別や偏見のない社会、子ども達の豊かな育ちを保障する社会、ジェンダー平等の社会をめざしとりくもう。
□ 各単会の運動に連帯し、支えあおう。会員の交流と親睦を深め、生きがい活動にとりくもう。東アジア各国との連帯・交流をすすめよう。組織拡大と財政確立、日教組退職者組織の統一をめざそう。
戦後80年 被爆80年にあたっての特別決議
2025年は敗戦後80年、広島・長崎被爆後80年になります。加えて、東京大空襲をはじめとする大都市空襲から80年になります。
負けるとわかっている戦争に国民を動員し、終戦の時機を逸して多くの国民を死地に追いやった、暗寓な指導者によってもたらされた大惨事である15年戦争。アジアで2000万人が犠牲になりました。
戦後50年、閣議を経てだされた「村山談話」では「私たちは過去のあやまちを2度と繰り返すことのないよう、戦争の悲惨さを若い世代に語り伝えていかなければなりません。」とし、「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。私は、未来に誤ち無からしめんとするが故に、疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここにあらためて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします。」と反省の弁を述べています。
戦後70年、安倍談話では、かつての日本の行為が「侵略」であったと直接言及することも避けていて、「痛切な反省」と「おわび」についても、過去の談話を引用する形での言及にとどめ、首相自身の言葉としては語らず、首相自ら直接謝罪を表明することも避けています。また、「あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」と過去の戦争と区切りをつけて、安倍首相は、「戦争準備」に取り掛かりました。
2014年に「集団的自衛権行使容認」を閣議決定し、2015年9月、安保法案(戦争法案)を強行可決し、「専守防衛」に徹するとした国の防衛方針を切り替え、「戦争する国」へと変質させました。さらに「共謀罪」を強行、「安保3文書」を改定し、「先制攻撃」を可能とし、GDP2%への防衛費増額を明記しました。さらに「軍需産業支援法」、「防衛装備移転三原則運用指針改定」と軍備増強路線を突っ走っています。
戦争末期、広島に投下された原爆、ウラン濃縮型「リトルボーイ」は、8月6日午前8時15分17秒に投下され、広島市の人口35万人中9万〜16万6000人が被爆から2〜4か月以内に死亡しました。
長崎に投下された原爆「ファットマン」は濃縮プルトニウム型で、長崎市の人口24万人(推定)のうち約7万4千人が死亡しました。
東京大空襲は、3月10日浅草区を中心とした人口密集地に、眠りについた深夜、ナパーム(ゼリー状ガソリン+起爆装置)爆弾を集中投下して、消火を超える高温による火災の広がりにより、わずか2時間の空襲で死者は10万人を超えました。以後、続く名古屋、大阪等各都市の空襲は東京大空襲方式による被害で20万人以上の死者を出しています。
東京大空襲、広島原爆投下、長崎原爆投下による被害者の1割以上は、強制連行を含む朝鮮半島からの出身者であることを銘記しなければなりません。
ロシアのウクライナ侵攻と原発使用の恫喝、イスラエルのガザ侵攻等世界は新たな分断に晒されています。
戦後80年の今、唯一の原爆被害国として、戦争被害を身をもって体験し、核兵器の廃絶や被爆の実相に対する理解の促進に取り組んできた日本被団協がノーベル平和賞を受賞しました。平和憲法を有する我が国こそ、核兵器禁止条約を批准し、核兵器の廃絶と戦争の愚かさとを世界に訴えて、平和を実現していくべきです。
私たち日退教は、憲法を守り、世界の平和の構築に向けて全力で取り組みます。
以上決議します。
総会宣言
ロシアによるウクライナ侵攻開始から3年4か月、イスラエルのガザ侵攻開始から1年7か月、いまだ停戦が実現できず、市民の犠牲は増え続けています。
アメリカ、トランプ大統領は、関税の引き上げや多国間協定の見直しを通じて、国際的な連携よりも国内の利益を優先する方向を強めています。
国内を見れば、「戦争をする国づくり」へ防衛費の拡大が続いています。自公政権は、2014年に「集団的自衛権行使容認」を閣議決定し、「戦争する国」へとまっしぐらに突き進んでいます。さらに「共謀罪」を強行、「安保3文書」を改定し、「先制攻撃」を可能とし、GDP2%への防衛費増額を明記しました。また日米で、「自衛隊による米軍基地等の共同使用、南西諸島を含む地域において、日米の施設の共同使用・共同演習・訓練を増加させる」「弾薬の南西諸島等島嶼部への分散配置を促進する」として、急ピッチでミサイルを配備しています。
辺野古では、国による代執行で大浦湾側の工事が強行され、キャンプシュワブゲート前での大型車両での工事用資材搬入阻止、塩川港や安和桟橋から土砂積み出し阻止に向けて座り込み闘争を闘っています。
石破政権は、第7次エネルギー基本計画を発表し、これまで基本計画で記載されてきた「原発依存度の可能な限りの低減」との文言は削除されました。2040年には電力の20%程度を原発に依存すると発表し、柏崎刈羽原発をはじめ、各地での原発再稼働への動きを強めています。
物価上昇が続いています。厚生労働省が発表した2024年度の実質賃金は前年度から0.5%減少し、3年連続のマイナスとなりました。
石破政権は物価高対策など生活保障を後回しにし、夫婦別姓の実現など人権保障を無視し、教育格差の中で子どもたちの教育を受ける権利が脅かされています。また、年金の削減、医療費の窓口負担増、健康保険料・介護保険料の負担増等、高齢者を標的に社会保障への攻撃が厳しさを増しています。
2025年は、日本の敗戦から80年目の年です。また、被爆から80年目を迎えます。平和憲法のもとに、誓いを新たに、石破政権がすすめる「戦争する国」づくりに反対し、憲法に基づく平和を守り抜きます。辺野古新基地建設に反対し、沖縄を再び戦場にすることを阻止します。原発再稼働、新・増設に反対し、脱原発を実現します。
医療・介護制度の改悪を許さず、社会保障制度の充実を実現していきます。人権が尊重され、差別や偏見、格差のない社会、ジェンダー平等な社会、子どもたちの豊かな育ちを保障する社会を実現していきます。
確認された活動方針に基づき、全力で取り組みます。
以上宣言します。
2025年6月6日
日本退職教職員協議会 第51回定期総会
23・24年度活動方針(2023年6月9日50回定期総会)
Ⅰ 特徴的な情勢
1 コロナ禍の世界、ロシア・ウクライナ戦争
新型コロナウイルス感染は、日本ではこれまでおおよそ3,400万人が感染しました。死亡者は7万人に達しました。
世界では、7億6千万人以上が感染し、死者は690万人に至っています(2023年5月1日)。コロナ感染によって、世界の工場が操業中止に追い込まれ、流通が破壊され、モノの流れが止まりました。ロシアのウクライナ侵攻と相まって物価が高騰しました。インフレ退治に各国は、公定歩合の引き上げを行った結果、地方銀行に金詰りが生じ、金融不安が起きています。
長引く感染症で国民は苦しい状況にあり、まして高齢者は物価高騰の中、医療費の自己負担の大幅上昇、年金の実質切り下げにより、厳しい生活を余儀なくされています。
ロシアのウクライナ侵攻開始から1年を超えました。ウクライナでの戦争は、NATO対ロシアの戦争の色合いが強まり、停戦がますます困難になってきています。
この戦争は世界の食料不足、エネルギー危機を招き、コロナの影響もあって、インフレを招く事態になりました。「戦争に勝者はいない」と言われています。犠牲者を食い止めるために停戦を実現させなくてはなりません。
2 岸田政権の憲法改悪の動き
昨年7月8日、安倍元首相が狙撃され死亡しました。狙撃犯と家族の生活破壊、安倍氏と「統一教会」の深い関係、政界に根を張ったカルト集団の実態、また、改憲や家族の在り方等、「統一教会」の政策への関与が明らかになりました。
岸田政権は、安倍氏について、9月27日に多額の国家予算を使って法的根拠のない「国葬」を行いました。安陪氏の首相在任中の平和・民主主義・人権に敵対し、戦争する国への転換と、モリ・カケ・サクラに見られる政治の私物化・腐敗の実態を無いことにするためでした。
先ごろ開かれたG7サミットでは、こともあろうに被爆地広島で核兵器禁止条約には一言も触れないばかりか、「核抑止は防衛目的」のためだとして、核兵器を「正当化」しました。
安倍氏の遺志を継がされた岸田首相は、今次国会において「任期中に憲法改正を実現したい、憲法改正は先送りできない課題であり、こうした考えはいささかの変わりもない」と発言しています。
衆議院憲法審査会では、自公は維新の会、国民民主党を巻き込んで、とにかく審査会の開催を重ねて、改憲発議に向けて突き進んでいこうとする姿勢が明らかになっています。
日退教は、憲法前文にある「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」するとした憲法理念を今こそ胸に刻み、日教組、平和フォーラム、戦争させない1000人委員会と連帯して「教え子を再び戦場に送るな」の決意のもと、戦争をさせないためのとりくみが必要です。
3 安保三文書改訂と防衛費倍増
アメリカは、日本に対してNATO諸国並みの軍事費増大を求め、岸田政権は唯々諾々とアメリカに追随し、防衛予算を2倍にし、「安保3文書(国家安全保障政策、国家防衛戦略、防衛力整備計画)」改定を閣議決定しました。防衛費の予算水準を現在の国内総生産(GDP)の2%を目指すとなれば日本は世界3位の軍事大国になります。
国家防衛戦略では、周辺国への認識として、中国については、「対外的な姿勢や軍事動向等は、我が国と国際社会の深刻な懸念事項であり(中略)これまでにない最大の戦略的な挑戦」としました。北朝鮮については、「従前よりも一層重大かつ差し迫った脅威」としました。ロシアについては、「中国との戦略的連携強化の動きもあいまって安全保障上の強い懸念」として、緊張を煽っています。
これまで、日本は「非核三原則」を守り、他国に脅威を与える「軍事大国」にならず、相手から武力攻撃を受けたときに防衛力を行使する「専守防衛」に徹するとしてきました。こうした安全保障政策を大転換させて、相手の領域で有効な反撃を加えることができる「敵基地攻撃能力」を保有するとしました。
岸田首相の訪米に合わせて行われた、日米2+2会議で、「自衛隊による嘉手納弾薬庫地区の追加的な施設の共同使用、日本の南西諸島を含む地域において、日米の施設の共同使用を拡大し、共同演習・訓練を増加させる」「弾薬の島嶼部への分散配置を追求、促進する」として、先島諸島のミサイル基地化と日米共同使用を可能としました。「琉球新報」によれば、先島諸島ではアメリカ海兵隊のミサイル基地は、無人化し、遠隔操作で動く最新式の発射機を使う地対艦ミサイルにするとしています。海兵隊の犠牲をなくす一方、沖縄住民を危険に晒す状況を作り出しています。
2021年に強行可決された「重要土地等調査規制法」により、思想・良心の、表現の自由、プライバシー権などを侵害される危険性が指摘されています。同時にこの法律は、多くの制限を設け、軍事強化に反対する取り組みを困難にしています。
4 脱原発に逆行
岸田首相を議長とする「GX実行会議」は、昨年12月に「GX基本方針」を決めました。
そこには次のような原発推進を軸とする内容が含まれています。
・原子力を最大限利用する。原発再稼働を進め、電源構成で「2030年度に原子力比率20~22%」(第6次エネルギー基本計画の目標)を達成する。
・原発の建て替え・新設も行う。新たな安全メカニズムをもつ次世代革新炉の開発・建設に取り組む。
・「原則40年、最長60年」とされる原発の運転期間の延長を認める。
・六ケ所再処理工場の竣工など核燃料サイクルを推進する。
福島原発事故から12年、倒壊の危険性さえ指摘されている事故炉は、廃炉の道筋が見えてきません。「原子力緊急事態宣言」が解除されない中での、原発推進へ転換は許されることではありません。また、汚染水の海中投棄が計画に乗ってきました。
2010年から2020年の10年間で、使用される電力は12%削減されています。日本の人口は今後減少することは明らかで、当然使用電力は増えることはありません。今こそ、脱原発を実現し、再生エネルギーへの変換を行うべき時です。
5 辺野古新基地建設反対
「安保三文書」の中で、沖縄軍事化について「南西地域の空港、港湾の整備強化、利用拡大・住民避難の迅速化・陸自15旅団を師団に・重要司令部の地下化・自衛隊施設の防護対策」1兆7千億円の記述があります。これは沖縄の最前線基地化に他なりません。
昨年9月11日の沖縄県知事選挙では、現職の玉城デニー氏が2回目の当選を果たし、沖縄県民の意思・新基地建設反対が改めて示されました。
しかし岸田政権は、沖縄県民の意思を踏みにじり、辺野古新基地建設を強行しています。
新基地建設地のキャンプシュワブ東岸の大浦湾に面した埋め立て予定地の海底には「軟弱地盤」があり、地盤強度を示す「N値」はゼロの「マヨネーズ状態」で、到底基地としての使用に耐えられないものです。
玉城知事は、存在する軟弱地盤を理由に防衛庁の設計変更に許可を与えなかったことについて、防衛庁は一国民に偽装して「行政不服審査法」を使い、国交省に申し立てを行いました。
これまで、普天間飛行場所属のオスプレイやヘリの墜落、部品落下、不時着などの事故、トラブルが相次ぎました。県は米軍に対策を申し入れたが、日米地位協定のため、申し入れは届いていません。
米軍嘉手納基地と周辺の河川や地下水で、高い濃度の有機フッ素化合物(PFAS)が検出されています。PFASは化学物質審査規制法上、難分解、高蓄積、人や高次捕食動物への長期毒性のおそれから、国内での製造・輸入・使用が原則禁止される第一種特定化学物質に指定されており、沖縄県民の命と安全に関わる重大な問題になっています。米軍は、地位協定を盾に県の立ち入りをかたくなに拒否しています。
米軍キャンプシュワブ、ゲート前では、今も連日、新基地建設に反対する市民が抗議活動を続けています。
日退教は、3月に第11次沖縄連帯交流団を構成し派遣・交流を行いましたが、普天間基地撤去・辺野古新基地建設反対の運動は「沖縄の運動」ではなく私たちの運動として、ひきつづき沖縄県・高両退教とともにとりくみます。
6 少子高齢化と社会保障(含教育)を取り巻く情勢
(1)65歳以上の高齢者は、2015年の 3,387 万人から、22年には 3,627 万人へと増加し、第二次ベビーブーム世代が老年人口になる42年に 3,935 万人でピークを迎えます。
一方、厚生労働省が発表した、22年の人口動態統計速報によれば、22年の出生数(外国人なども含む)は79万9,728人となり、1899年の統計開始以降で初めて80万人を割り込み、過去最少を更新しました。2040年には65歳以上の人口が35.3%、75歳以上は20.2%となり、未知の「超少子・高齢社会」に突入します。
(2)「社会保障の全体像をいま一度俯瞰し、その再構築を図る」ことを目的に議論を進めてきた、「全世代型社会保障構築会議」は、昨年12月16日、報告書を発表しました。「全世代型社会保障」の将来方向として、次の3点をあげています。
① 「少子化・人口減少」の流れを変える
② これからも続く「超高齢社会」に備える
・ 働き方に中立的な社会保障制度を構築し、労働力を確保する
・ 社会保障を皆で支える仕組みを構築し、ニーズの変化に的確に対応する
③ 「地域の支え合い」を強める
分野ごとの改革の方向性や工程を整理したとしていますが、肝心の少子化対策は財源議論が手つかずで、今夏まで先送りになり、「持続可能な社会保障の全体像」を十分に描けたものとはいえず、さらに今後の議論に引き継がれます。会議と並行して社会保障審議会各部会の議論も再開され、当面の施策の法案化、や継続課題の整理が行われています。
岸田首相の「異次元の少子化対策(経済支援・サービス充実・育休強化)」は財源論抜きでの議論が進んでいます。6月の骨太方針までに具体策を示すとされていますが、防衛費倍増に向けての予算措置は着々と進めながら、これについて示さないのは無責任です。
2023年1月20日、厚労省は2023年4月からの年金額について、新規裁定者(67歳以下)は2.2%、既裁定者(68歳以上)は1.9%の引き上げを公表しました。新規裁定者は賃金の上昇に伴う年金改定で、既裁定者は物価上昇に伴っての年金額の改定でした。新規裁定者と既裁定者に分かれての年金改定は、2004年に現制度ができて初めての適用でした。
7 ジェンダー平等
2020年の早い段階から、コロナの影響により、企業の実績悪化から非正規の雇用削減が行われました。2020年7月から9月にかけて、正規の対前年度比の雇用減0.5%に対し、非正規の雇用減は6.7%になっています。非正規の7割が女性であることから、雇用減が女性に集中しました。
コロナによる外出制限に伴い、家庭内の家事・育児等の無償労働が集中する、女性に多くの負担をかけることになりました。突然の指示で始まった、多くの休校・休園にともない育児の時間が増え、小さな子どもを抱える女性の就業者数が減る結果になりました。2020年、男性の自死者は減る中、女性の自死者は15%もの大幅な増加でした。
2月4日、性的少数者「LGBT」や同性婚への差別発言があり、荒井首相秘書官が更迭されました。政府自身が性的少数者を自死のハイリスク層である(厚生労働省「自殺対策総合大綱」)としているにもかかわらず、政府の中枢から差別発言が出て、性的少数者を更に追い詰めています。「LGBT理解増進法案」をめぐっては、与党案、立憲民主・共産・社民の3党案、日本維新の会と国民民主党案の計3案が国会に提出されています。
女性差別撤廃条約は、1979年の第34回国連総会において採択され、1981年に発効しました。日本は1985年に締結しました。この条約の実効性を強化するために、1999年、「個人通報制度」と「調査制度」を盛り込んだ「女性差別撤廃条約選択議定書」が採択されましたが、日本はまだ批准していません。批准できれば、個人通報制度を利用して「男女差別賃金の是正」「選択的夫婦別姓の実現」にむけて、前進することができます。
国連サミットで採択されたSDGsの5番目の目標に「ジェンダー平等」が掲げられていて、「ジェンダー平等を達成し、すべての女性と女児の能力強化を行う」こととするとなっています。しかし、日本の2022年のジェンダーギャップ指数は146か国中で116位です。
ジェンダーによる格差を解消するには性別役割分業やそれを支えている制度、そしてアイコンシャス・バイアス(無意識の偏見)の見直しが必要です。またDVや虐待など、家庭が女性や子供にとって必ずしも安全な場所ではない現実を直視し、個人にとって公平で安全な社会に向けてジェンダー主流化を「予算を伴う政策」としての具体化が必要です。
8 組織
(1)2022年8月1日付の日退教の組織・会員は、2021年に比べて約1000人の減少になっています。2023年度から定年が延長され、2024年3月には定年で退職する人がいません。現職との交流をより緊密にして、現退一致しての組織拡大が必要です。既定年退職者の会員化のとりくみ等を組織活動交流集会で交流し、会員加入に努力していく必要があります。
(2)2022年7月に実施されました第26回参議院選挙において、古賀ちかげ日政連議員候補は現退一致した取り組みで、144,344票を獲得し、立憲民主党の全国比例第3位で見事当選を勝ち取りました。立憲野党が議席を減らす中、自公が改憲に必要な3分の2を確保しました。
現在、選挙の争点にしなかった「先制攻撃」「軍事費倍増」等が盛り込まれた「安保三文書」改定が閣議で決定されるなど、岸田政権のもと、独裁的政治が強行されています。
2023年4月の統一地方選挙において、日政連候補者は109人でした。現退一致のたたかいの結果、ほぼ全員の当選を勝ち取りました。しかし地方選挙全体を見れば低投票率に終わり、自民政権に打撃を与える情勢は作りえませんでした。
Ⅱ 具体的要求・当面の活動
1 憲法「改正」に反対し、平和・人権・環境が尊重される社会をつくります
具体的要求と活動
(1)憲法改悪阻止、立憲主義を取り戻すため、日教組・平和フォーラムとともに積極的にとりくみます。
各県・地域でとりくまれる「戦争をさせない1000人委員会」「総がかり行動」「さようなら原発1000万人アクション」の活動等に積極的に参加します。
「戦争法」「共謀罪」「特定秘密保護法」の廃止を求めます。
防衛費の大幅増に反対します。
(2) 普天間基地の即時運用停止、辺野古新基地建設阻止のために、沖縄両退教との連携をさらに強め、とりくみます。
日退教沖縄交流団を派遣します。単会やブロック単位で沖縄の状況を理解し連帯を強めるための学習会や現地行動参加にとりくみます。また、全国各地の米軍基地反対闘争・合同演習反対運動に積極的に参加します。
(3) 日米地位協定の問題を追及し、改定を求めてとりくみます。
(4)「台湾有事」等軍事的緊張を煽る日本政府の姿勢を厳しく批判し、朝鮮戦争の終結、平和協定締結、朝鮮半島の非核化、東アジアの平和的安定を求めとりくみます。
(5) 朝鮮学校への差別的扱いに反対し、朝鮮学校への補助金・助成金等の支給停止反対運動をすすめます。朝鮮学校生徒の「高校無償化」を支援します。ヘイトスピーチを許さず、東アジアをはじめとする諸国の人々と友好と連帯・交流を深めます。
(6) 狭山事件の再審開始を求めるとともに、えん罪根絶に向けた司法改革・再審法改正、部落差別をはじめあらゆる差別解消に向け、人権侵害救済制度の確立を平和フォーラム等とともに取り組みます
(7)「女性差別撤廃条約選択議定書」の早期批准を求めます。女性の経済的自立と意思決定の場における発言力を高めることが、日本のジェンダー平等を実現するために不可欠です。「政治分野における男女共同参画推進法」の趣旨に沿ったとりくみを地域ですすめます。さらに、「同一価値労働同一賃金」の実現を、女性の人権を国際的水準に引き上げる運動の要としてとりくみます。
(8) 立憲主義を取り戻し、当たり前に生きることのできる社会をつくるため、各種選挙での日政連・各単会推薦候補の必勝をめざしとりくみます。
2025年7月に実施される第27回参議院選挙には水岡俊一現参議院議員を推薦し、当選をめざします。各単会は、水岡俊一さんを推薦決定し、勝利するよう現退一致で取り組みます。
2 「教育改革」の危険性と民主教育を守るとりくみ
具体的要求と活動
(1) 憲法改悪反対のとりくみと連動し、復古的家族主義、国家主義的教育を許さないようとりくみます。
各地域で行われる県教組・高教組、関連団体の主催する学習会・集会に積極的に参加します。
(2) 政治による教育への不当な支配に反対します。国・地方議会における教育現場介入の動きを許さないよう議会監視にとりくみます。
(3) 国の定める「統一基準」による「検閲」検定に反対します。次期教科書採択にむけては、各地域における展示会への参加や学習会への参加にとりくみます。
(4) 貧困・格差を許さないため、教育の無償化へのとりくみを強化します。
3 原発再稼働を許さず、脱原発に向けたとりくみ
具体的要求と活動
(1) 脱原発社会実現のため、政府のGX(グリーントランスフォーメーション)に名を借りた原発建て替え、再稼働・新設・稼働延長に反対し、各地で行われる諸行動に積極的に参加します。
(2) 震災を受けた地域の復興がさらに長期間かかることを念頭に、被災者の万全な生活・居住対策を政府・自治体に要求します。1947年制定のままの災害救助法の見直しを求めます。
(3) 自然(再生可能)エネルギー普及のための法・制度の充実を求めていきます。
(4) 高速実験炉〚常陽」の速やかな廃止、「もんじゅ」の廃炉作業の安全性確保、全ての原発を停止するよう求めます。
(5) 各地の自然エネルギー利用のとりくみに協力します。廃炉費用、福島原発事故処理費用の原則事業者負担を求め、託送料に上乗せすることに反対します。
(6) 4野党共同で提出された「原発ゼロ基本法案」の国会での早期審議入りを求め運動します。
(7) 妊産婦、乳幼児・子どもなど若年者の被曝を防ぐ万全の対策を求めます。住民(避難民を含めて)の精密な医療検査と治療システムの確立を求めます。
(8) 「さようなら原発1000万人アクション実行委員会」の運動に参加し、「1000万署名」の達成、各種集会等の成功をめざしてとりくみます。
(9) 「連合・東北子ども応援わんぱくプロジェクト」「子どもの人権連・助成事業」のとりくみに協力します。高校生平和大使などの若者による運動のとりくみに協力します。
(10) 福島学習の旅を企画します。
4 格差是正、社会保障の充実・発展、生活を守り、増税に反対するとりくみ
具体的要求と活動
(1)抜本的な物価高騰対策を求めます。低賃金労働者、低年金者、子育て世帯、生活保護世帯、勤労学生などへのきめ細かな現金給付を中心とした支援の実施を求めます。
(2)基礎年金はマクロ経済スライドの対象外とすることを求めます。短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、速やかにかつ抜本的に拡大すること、また国民年金保険料拠出期間延長(拠出期間を40年から45年に)を求めます。
(3) 介護保険の被保険者を医療保険加入者全体に拡大することの是非を検討します。ケアプランの有料化、「要介護1・2の総合事業移行」に反対します。 利用者負担原則1割維持を求めます。介護認定基準の見直し・改善を求めます。
(4) 公的皆保険制度を堅持させ、国民健康保険の財政基盤を確立し、低所得者に対する対策を講じて無保険者を発生させないことを求めます。医療を市場化する一部「混合診療」に反対します。
「75歳以上の医療費定率負担2割の所得基準切り下げ」「所得に加え金融資産等を算定基礎とした患者負担」に反対します。「医療・介護両制度の違いを無視した横並びの負担増・給付抑制」をやめることを求めます。保険証を廃止して『マイナ保険証』に一本化することに反対します。
(5) 高齢者虐待防止法の適正・的確な運用を求め、被介護者本人の意思を尊重する社会的介護をすすめる「介護共生社会」をめざして介護保険法改善要求を強めます。また、介護従事者の賃金改善を要求します。
医療・介護の切れ目のない地域包括ケアシステムを実体化するため、地域包括ケアの要である「地域包括支援センター」の機能と財政基盤の強化を求め地域密着型サービスを拡充することを求めてとりくみます。
(6) GPIF経営委員会の構成割合は労使代表を過半数とすることを求めます。
(7) 累進課税強化、金融所得課税是正を求め、消費税増税による、法人税減税肩代わりに反対します。金持ち優遇の軽減税率に反対します。「給付付き税額控除」の導入を求めます。
5 組織の拡大、強化のとりくみ
具体的要求と活動
(1) コロナ感染拡大に伴う厳しい状況下にあっても創意工夫に努め、親睦・交流・運動を通じて、退職者同士のつながりを強め、会員の孤立を防ぐよう努めます。現職組織との交流を重ね、組織拡大については現職の協力を得てすすめます。現職、再任用、退職者と切れ目のない組織化を追及します。
(2) 各単会は各現職組合に働きかけ退職者組織加入方針化を追求します。同時に共同行動を積み上げます。また、再任用者を退職者組織対象(現職組合との二重加盟も視野に)とするよう現職組合との協議をすすめます。
(3) すべての県に日退教組織を作り上げるよう日教組・各県単組と連帯してとりくみます。また、地方退職者連合組織未加盟単会は加盟を追求します。
(4) 毎年5月・6月を組織拡大月間としてとりくみます。8月1日現在の組織現況・実態を調査します。組織拡大のとりくみ、日退教・各単会の組織状況・実態については、10月の組織活動交流集会で交流します。
(5)定年延長に伴って困難になる組織拡大の取り組みについて交流します。
(6) 組織活動交流集会は、「組織」「平和」「教育・人権」「福祉・文化」を主題におこないます。すべてのブロックからのレポートの提出ができるようにとりくみます。女性参加者の拡大にとりくみます。
(7) 五者合同学習会を日教組、全国退女教、教職員共済生協、日本教職員相互共済会共催で実施します。
(8) ジェンダー平等の観点にもとづき、女性会員の拡大、運動の充実に努めます。各種活動・集会、意思決定機関・役員への女性参画を高めるよう努めます。退職者連合のジェンダー平等委員会の活動に積極的に参加します。研究・検討・学習・論議を含めた運動を通じて日教組退職者組織の一本化をめざします。
(9) 各単会との緊密な交流・連携体制を強めます。各単会の運動に連帯し、支えあいます。「日退教通信」は会員の交流の場としての機能をさらに強化充実します。年に1~2回は、全会員に配布します。日退教のホームページの活用を充実します。
(10) 日退教運動の拡がりと財政状況を踏まえ、組織・財政を見直します。引き続き、定期総会は隔年開催とし、定期総会を開催しない年は組織代表者会議を開催し、当面の活動を確認します。組織代表者会議の構成は各単会1(組織代表者)、ブロック女性代表者各ブロック1とします。
(11) 組織財政確立委員会(各ブロック代表者兼務)を引き続き設置し、将来の収入見直しに基づく組織運営、事務局体制の検討を行います。
(12) 23年度日退教闘争カンパにとりくみ、各種運動に活用します。
(13) 退職後の会員互助を充実するため、教職員共済生協、日本教職員相互共済会、退職教職員生きがい支援協会などの運営・運動に参加します。
(14) 平和憲法を守り、脱原発社会の実現、社会保障制度の確立を求め、日教組、退職者連合・地公退、平和フォーラムに結集し運動にとりくみます。
日退教第50回定期総会 スローガン
教え子を再び戦場に送るな
- □ 期衆議院・参議院選挙に勝利し、改憲を阻止しよう。防衛費の増大に反対し、軍拡を許さずたたかおう。沖縄と連帯し、辺野古新基地建設をとめよう。日米地位協定の抜本的見直しをめざそう。
- □ 東日本大震災・福島第一原発事故を風化させず、被災者・被害者の生活支援打ち切りに反対し、国・企業の責任を追及しよう。原発再稼働、新・増設、輸出に反対し、脱原発社会をめざそう。核兵器禁止条約の早期批准をめざしとりくもう。
- □ 医療・介護・年金制度の改悪を許さず、社会保障制度の改善・充実を求めよう。格差社会の是正をめざしとりくもう。
- □ セクハラ・パワハラを許さず、ジェンダー平等の社会、人権が尊重され、差別や偏見のない社会、子ども達の豊かな育ちを保障する社会をつくろう。
- □ 各単会の運動に連帯し、支えあおう。会員の交流と親睦を深め、生きがい活動にとりくもう。東アジア各国との連帯・交流をすすめよう。組織拡大と財政確立、日教組退職者組織の統一をめざそう。
総会宣言
「岸田首相が『長年の平和主義を捨て去り、自国を真の軍事大国にすることを望んでいる』」とアメリカのタイム誌は紹介しました。
岸田政権は、防衛予算を倍増させ、先制攻撃を可能とする「安保三文書」を閣議決定し、今国会で関連法案の成立を強行しようとしています。中国に対しては、「わが国と国際社会の深刻な懸念事項」と挑発し、トマホークを導入するなど、米軍のシステム「統合防空ミサイル防衛」の傘下に入り、戦争する国づくりに邁進しています。
帰還困難地域がいまだ広範囲に残り、「原子力緊急事態宣言」が解除されない福島原発事故。この事故の教訓に学ばず、岸田政権は原発稼働上限を60年超えに延長、さらに再稼働、新・増設を「GX(グリーン・トランスフォーメーション)」の名のもとにすすめようとしています。同時に、汚染水の外洋投棄をこれまた強行しようとしています。
沖縄では、県民の意思に背いて辺野古新基地建設を強行しています。空港・港湾の日米共同利用を可能とし、馬毛島・奄美大島から沖縄本島を経て先島までをミサイル基地化し、九州・沖縄を再び戦場とする危険に晒しています。
昨年10月から、後期高齢者医療費の窓口負担2割が導入され、さらに後期高齢者医療保険料増額も予定されています。今年4月の消費者物価指数は昨年同月に比べ3.5%上昇していて、実質賃金は3.0%減で13か月連続マイナスとなっています。4月から68歳以上の年金は1.9%引き上げられましたが、退職者の生活は一層厳しくなります。
改正マイナンバー法が成立しました。構造的な欠陥と不備を放置したまま健康保険証を廃止すれば、国民皆保険崩壊も懸念されます。マイナ保険証への一本化強行に反対します。
今年度から教職員の定年が延長されます。日退教にとって組織の拡大は喫緊の課題です。コロナ禍を経験して、「対面」での交流・親睦の大切さを学びました。仲間づくりをすすめます。
岸田政権がすすめる「戦争する国」づくりに反対し、憲法に基づく平和を守り抜きます。辺野古新基地建設に反対し、沖縄を再び戦場にすることを阻止します。原発再稼働、新・増設に反対し、脱原発を実現します。
医療・介護制度の改悪を許さず、社会保障制度の充実を実現していきます。
人権が尊重され、差別や偏見、格差のない社会、ジェンダー平等な社会、子どもたちの豊かな育ちを保障する社会を実現していきます。
私たちは今次総会で確認した活動方針に基づき、全力でとりくみます。
以上宣言します。
2023年6月9日
日本退職教職員協議会 第50回定期総会